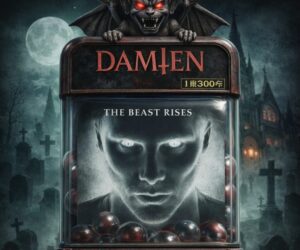1977年6月。日本の映画興行史において、ある一つの事件が起きた。 「決してひとりでは見ないでください」 このあまりにも有名なキャッチコピーとともに公開されたイタリア映画『サスペリア』は、それまでのホラー映画の文脈を完全に破壊した。 物語の整合性や伏線の回収といった文学的な手続きを一切無視し、視覚と聴覚、そして空間認識能力という人間の生理的な感覚器に対して直接的な暴力を振るうこと。 ダリオ・アルジェント監督が目指したのは、映画というメディアを使った「悪夢のシミュレーション」に他ならない。
公開から半世紀近くが経過した現在、4Kレストア版の登場や、ルカ・グァダニーノによるリメイク版(2018年)の公開によって、オリジナル版の評価は神格化されつつある。 なぜ我々は、この古びた、非論理的な物語にこれほどまでに魅了され続けるのか。 そこには、現代のデジタルシネマが失ってしまった「物質的な恐怖」と、計算され尽くした「空間の魔術」が存在する。 本記事では、建築家である私の視点から、歴史的背景、映像技術、音響心理学、建築様式、そして象徴主義の観点を総動員し、この映画がなぜ芸術足り得るのかを5000字規模で徹底的に解剖する。
1. 時代背景:1970年代イタリア「鉛の時代」が生んだ集団的パラノイア
サスペリアの画面全体から漂う、肌にまとわりつくような不穏な空気。 これを単なるホラー映画の演出として片付けるのは早計だ。この空気感には、明確な歴史的根拠がある。
鉛の時代(Anni di piombo)の恐怖
1960年代後半から1980年代初頭にかけてのイタリアは、極めて不安定な社会情勢下にあった。これを「鉛の時代」と呼ぶ。 極左組織「赤い旅団」やネオ・ファシスト勢力によるテロリズムが吹き荒れ、政治家の誘拐、暗殺、広場での無差別爆破事件が日常的に発生していたのだ。 1969年のミラノ・フォンターナ広場爆破事件を皮切りに、市民生活は常に死と暴力の隣り合わせだった。
相互監視と疑心暗鬼
「誰が敵で誰が味方かわからない」「隣人がテロリストかもしれない」。 そのような疑心暗鬼(パラノイア)が社会全体を重く覆っていた。 アルジェント監督は、このイタリア社会の閉塞感を、ドイツのフライブルクにあるバレエ学校という「閉鎖空間」に移植したのだ。 外部との連絡が遮断され、内部では理不尽な規律が支配する。 夜になると聞こえる不気味な足音、どこからともなく感じる視線。 これらは、当時のイタリア市民が実際に感じていた「見えない暴力への恐怖」のメタファーである。 映画という虚構の枠組みを使いながら、アルジェントは同時代の空気をドキュメンタリーのようにフィルムに焼き付けていたと言えるだろう。
2. 神話的構造:トマス・ド・クインシーと「三人の母」の概念
多くの観客は『サスペリア』を単発の魔女映画だと思っているが、その背後には壮大な神話体系が存在する。 その設計図となったのが、19世紀イギリスの作家トマス・ド・クインシーによる散文詩『深き淵よりの嘆息』だ。
三人の母(The Three Mothers)
アルジェントと共同脚本のダリア・ニコロディは、この詩に登場する「三人の母」という概念を映画の世界観に取り入れた。
-
涙の母(Mater Lachrymarum):ローマを支配する、最も美しく残酷な母。
-
嘆きの母(Mater Suspiriorum):フライブルクを支配する、最も年長で知恵に長けた母。本作の敵役。
-
闇の母(Mater Tenebrarum):ニューヨークを支配する、最も若く残忍な母。
本作『サスペリア』に登場するのは「嘆きの母」である。 彼女は物理的な力でねじ伏せるというよりは、人々の精神を蝕み、ため息とともに絶望や病をもたらす存在として描かれる。 だからこそ、この映画の恐怖は直接的なスラッシャー描写よりも、精神的な圧迫感(サスペンス)に重きが置かれているのだ。 この三部作構想(『サスペリア』『インフェルノ』『サスペリア・テルザ』)を知ることで、本作の不可解な描写の多くが、実は神話的な必然性に基づいていることが理解できるはずだ。
3. 映像技術の極北:絶滅した「テクニカラー」による色彩の暴力
私がこの映画を評価する最大の理由は、その色彩設計にある。 画面を埋め尽くす、鮮血のような赤、毒々しい青、病的な緑。 これらは現代のデジタル・カラーグレーディングでは決して再現できない「物質としての色」だ。
テクニカラー・インビビション方式の採用
撮影監督ルチアーノ・トヴォリとアルジェントは、当時すでにコスト高と手間から廃止されつつあった「テクニカラー・インビビション方式(3色分解法)」を採用した。 通常のカラーフィルムは3つの感光層を持っているが、この方式では撮影したネガから赤・緑・青の3本の白黒分解ネガを作成する。 そして、それぞれの補色となる染料(イエロー、シアン、マゼンタ)をフィルムに直接「転写(Imbibition)」する。 これは写真というよりは「印刷」に近いプロセスだ。 染料を物理的に染み込ませるため、発色が極めて鮮やかで、経年劣化にも強い。 アルジェントはローマの現像所に残っていた最後の機械を無理やり稼働させ、この失われた技術を蘇らせた。
ディズニー映画『白雪姫』へのオマージュ
彼らが色彩の参考にしたのは、ウォルト・ディズニーのアニメーション映画『白雪姫』だった。 アニメーションの世界でしかあり得ない純度の高い原色を、実写映画に持ち込むこと。 その狙いは、観客の脳に対して「これは現実ではない、逃げ場のない悪夢なのだ」というシグナルを送り続けることにある。 特に「赤」への執着は病的だ。 壁紙、ベルベットのカーテン、衣装、マニキュア、ワイン、そして血。 画面内のあらゆる要素が深紅に染め上げられている。 色彩心理学において、赤は「危険」「警告」を意味すると同時に、「生命」「子宮」も象徴する。 観客はこの過剰な赤色光線に視神経をレイプされ続け、本能的な恐怖と、胎内回帰的な奇妙な安心感を同時に植え付けられることになる。
4. 建築学的サディズム:空間操作とドアノブのトリック
建築家の視点から言わせてもらえば、この映画の真の主役は、ジェシカ・ハーパーではなく「建物」そのものだ。 舞台となるバレエ学校の外観は、ドイツのフライブルクに実在する「ハウス・ツム・ヴァルフィッシュ(鯨の家)」をモデルにしている。 後期ゴシック様式の重厚なファサードは、それだけで圧倒的な威圧感を放つ。
歪んだアール・ヌーヴォーの迷宮
内部のセットデザインは、アール・ヌーヴォー様式を基調としている。 植物的な曲線、ステンドグラス、幾何学模様のタイル。 一見美しく見えるが、そこにはマウリッツ・エッシャーの騙し絵のような、意図的な「歪み」が組み込まれている。 遠近法が狂った廊下、過剰に高い天井、どこに繋がっているか分からない階段。 これらの空間は、長時間見つめていると平衡感覚を狂わせる。
ドアノブの位置による退行催眠
そして最も巧妙な建築的トリックが「ドアノブの位置」だ。 アルジェントは、セット内のすべてのドアノブを、通常よりも高い位置に設置させた。 これは単なるデザインではない。 大人の女優がドアを開けようとするとき、彼女たちは無意識に手を高く上げ、顎を上げる姿勢を取らされる。 これは、幼い子供が大人用の重いドアを開けるときの身体動作そのものだ。 この物理的なギミックにより、観客の深層心理には「幼少期の無力感」がフラッシュバックする。 世界は自分よりも大きく、圧倒的で、自分は無力な子供であるという感覚。 これを私は「身体的記憶による退行催眠」と呼んでいる。 論理的な大人の視点を奪い、理不尽な恐怖に怯える子供の視点へと観客を強制的に引きずり込む。 実に陰湿で、計算され尽くした空間設計だと言わざるを得ない。
5. 音響テロリズム:ゴブリンによる聴覚への拷問
映像が右脳を刺激するなら、音楽は中枢神経を直接切断しに来る。 イタリアのプログレッシブ・ロックバンド「ゴブリン」によるサウンドトラックは、映画音楽の常識を根底から覆した。
撮影現場でのライブ演奏という狂気
通常、映画音楽は撮影が終わり、編集が完了した後に映像に合わせて作曲される(ポストプロダクション)。 しかしアルジェントは、撮影前にゴブリンに楽曲を制作させ、撮影現場に巨大なスピーカーを持ち込んで、その大音量を流しながら演出を行った。 画面の中の女優たちが浮かべる焦燥感、怯え、狂気。 あれは演技ではない。 実際にゴブリンの轟音という「音の暴力」に長時間晒され続け、精神的に追い詰められた人間の生理的反応なのだ。
悪魔的な楽器構成とサブリミナル
使用された楽器も特異だ。 ギリシャの民族楽器ブズーキの執拗なリフレイン、タブラの変則的なリズム、そして巨大なモーグ・シンセサイザーの電子音。 これらが奏でる不協和音に、「Witch! Witch!」と繰り返す悪魔的な囁き声や、金切り声が重なる。 さらに、人間の可聴域ギリギリの不快な高周波や重低音がサブリミナル的にミックスされているとも言われている。 これらは脳の偏桃体を直接刺激し、理由のない不安感や闘争逃走反応を引き起こすトリガーとなる。 美しい旋律で感動させることなど微塵も考えていない。 ただひたすらに、観客の神経を逆撫ですることだけを目的に構築された音響兵器だ。 4Kリマスター版を良質なサラウンドシステムで再生することは、ある種の自傷行為に近いかもしれない。
6. シークエンス分析:論理を超越した名場面の解体
この映画には、ストーリー上の必然性はなくとも、映像的な強度が極めて高いシークエンスがいくつも存在する。
空港からタクシーへの導入部
冒頭、主人公スージーがミュンヘンの空港に降り立つシーン。 自動ドアが開いた瞬間、轟音とともに吹き込む風と、極彩色の照明。 タクシーに乗り込むと、激しい雷雨の中、窓の外を流れる景色は現実のドイツの街並みではなく、抽象的な光の帯となる。 このタクシーの中で、一瞬だけ窓(あるいはバックミラー)に苦悶する男の顔が映り込む都市伝説的なシーンがあるが、あれは監督のアルジェント本人のカメオ出演だという説が有力だ。 観客の不安を煽るためのサブリミナル演出の一つだ。
盲導犬の反逆と広場のシーン
盲目のピアニストが、誰もいない広場で自身の盲導犬に喉を食い破られるシーン。 なぜ長年連れ添った忠犬が突然主人を襲うのか? 論理的な説明は一切ない。 だが、広場を支配する巨大な建築物の影、石畳の冷たさ、そして静寂から突如として訪れる獣の咆哮。 「安全だと信じていたものが牙を剥く」という不条理こそが、このシーンの本質だ。
針金部屋の悪夢
学校から逃げ出そうとした生徒が、大量の針金(ワイヤー)が張り巡らされた部屋に迷い込み、もがき苦しんで死ぬシーン。 なぜ学校の中にそんな部屋があるのか? そんな疑問を持つこと自体がナンセンスだ。 あれは「蜘蛛の巣」の視覚化であり、一度足を踏み入れたら二度と出られないという運命の暗示である。 痛々しい描写だが、その構図は残酷なほどに美しい。
7. 日本独自の宣伝戦略:昭和の興行師たちが仕掛けた「嘘」
『サスペリア』を語る上で、日本独自のコンテクストにも触れておく必要がある。 東宝東和という配給会社が行ったプロモーションは、ある種の詐欺スレスレだが、天才的な演出だった。
ショック死保険とサーカム・サウンド
「ショック死保険」。 上映中に恐怖のあまりショック死した場合、1000万円を進呈するという奇抜なキャンペーン。 もちろんこれは話題作りのギミックに過ぎないが、劇場窓口で医師らしき人物が聴診器を当て、観客に誓約書を書かせるパフォーマンスは効果絶大だった。 当時の子供たちは「本当に死ぬかもしれない映画」だと信じ込み、その恐怖と好奇心が劇場へと足を運ばせる原動力となった。 また「サーカム・サウンド」という独自の音響システムも宣伝された。 既存の劇場スピーカーに加え、数台のスピーカーを増設し、音が観客を取り囲むように調整したものだ。 「音が襲ってくる」という宣伝文句は、観客の恐怖体験を増幅させるプラシーボ効果として機能した。
『サスペリアPART2』の謎
そして極めつけは、翌年公開された『サスペリアPART2』だ。 原題は『Profondo Rosso(深紅の/赤い深淵)』であり、本来は『サスペリア』よりも2年前に製作された全く無関係のミステリー映画(ジャッロ)である。 だが日本の興行師たちは、これを「続編」として売り出した。 倫理的には問題があるが、この商魂たくましい戦略のおかげで、アルジェントの最高傑作の一つである『Profondo Rosso』が日本で広く認知されることになったのも事実だ。 昭和という時代の大らかさと、熱狂が生んだエラーである。
8. 結論:4Kで蘇る「美しき欠陥住宅」
『サスペリア』にストーリーの整合性を求めてはいけない。 それは、抽象絵画に「何が描いてあるのか」と問うのと同じくらい野暮なことだ。 アルジェントが構築したのは、左脳的な「理解」ではなく、右脳的な「体験」のための装置だ。
CG全盛の現代において、フィルムと照明とセットだけで構築されたこの「アナログな悪夢」は、オーパーツのように異質な輝きを放ち続けている。 現代のホラー映画は説明過多だ。 伏線はすべて回収され、動機は明確に語られ、観客を安心させるための論理的解決が用意されている。 だが、現実はそんなに単純ではない。 理由のない悪意、説明のつかない現象、抗えない運命。 『サスペリア』が描くのは、そうした「不条理」そのものだ。
もしあなたがこの映画をまだ未見なら、あるいはVHSやDVDの画質でしか記憶にないなら、ぜひ4K UHDなどの高画質版でこの迷宮に足を踏み入れてほしい。 ただし、スマートフォンの小さな画面で見るなどという建築物への冒涜は許されない。 部屋の照明をすべて落とし、可能な限りの大画面と、近所迷惑にならないギリギリの大音量を用意しろ。 そして一人で見ろ。 孤独な空間で、視覚と聴覚を完全にハッキングされる快感に身を委ねろ。
ラストシーン、炎上する学校を背にスージーが見せる謎めいた微笑み。 あれは恐怖からの解放なのか、それとも彼女自身もまた魔女としての資質に目覚めたことへの歓喜なのか。 答えなどない。 あるのは、論理を焼き尽くされた後に残る、奇妙な爽快感だけだ。

▼配信の画質で満足するな。真の「赤」を手元に